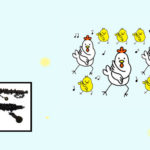夜で、本当に良かった・・・。
波和湯風太郎は、心の底から思っていた。
これがもしも、町人や商人が大勢行き交う昼間であったなら。
・・・風太郎は思わず、身震いをする。
武士というもの、必ず、道の真中を歩く。
これは城中であろうと、町中であろうと、変る事はない。
理由としてはまず、当時の身分制度がある。
つまり「士農工商」であるが、この制度の中では、武士が一番身分が高い。
だから堂々と、道の真中を歩くのだ。
また武士の作法とは、自然体でありながらも常に、己の身を守る術を取り入れているものだ。
たとえばこちらが、町の中で敵に奇襲をかけるとしよう。
目的のためにはまずは、建物の影か。
人の波に身を潜ませて、好機を探すに違いない。
・・・あらゆる物陰に潜んで機会を伺う訳だが、相手が道の端などを歩いていたら。
しめたとばかり、こちら側は物陰から刀で一突き。
一息に相手を、討てるというものだ。
それを防ぐという意味もあって、武士は道の真中を歩くのだ。
ところでこの日の風太郎と、気儘之介の出で立ちである。
風太郎は武士であるから、勿論羽織袴に帯刀した姿である。
よって道の真中を歩いていても、少しの不審もない。
・・・気儘之介である。  古ぼけた野良着に、ツギがあたった袴、おまけに刀まで差している。
古ぼけた野良着に、ツギがあたった袴、おまけに刀まで差している。
そんな奇怪な姿でいて、それでいてどことなく風格があったりするのはこの際、さすがといえばいいのか、何と言ったものか。
地味にして欲しいという風太郎の指示で、気儘之介には取り敢えず、手拭いを頭に巻かせてみた。
それがまた泥だらけで、雑巾にもならないような手拭いなのだ。
それでと言おうか、何と言おうか。 何をやってもどうも、違う方へと向かってゆくような・・・。
何をやってもどうも、違う方へと向かってゆくような・・・。
そして風太郎に付き合ってか、また堂々と道の真中を歩く気儘之介なのである。
ところで。
一昨年前までは、稽古の終った風太郎と気儘之介、源爺の店に毎日のように通っていた。
当然、共に道場に通う仲間もそれは知っているし、道中知らぬうちに出来た知り合いも多い。
道場を一歩出たところでまず、お梅婆さんに会ってしまった。 
・・・当時はよくこの婆さんの拵える飯で、二人が腹を満たしたものだ。
この婆さん。
世間では「気難し屋」で通ってはいるが、なに、気儘之介が可愛くて仕方がないのだ。
会えば嬉しくて、飯に誘う。
婆さんの住む長屋が、源爺の店に行く途中であるので、成り行きで送っていく羽目となった。
ところでお梅婆さんは、足は達者で声が大きい。
気儘之介が語る「武者修行の旅」の話に夢中で、それは熱心に相槌を打ち、その興奮した声は狭い長屋の隅々にまで届いてしまう。
 「・・・・・・気儘之介・・・。頼むから、人目に立つような事はできるだけ・・・・・・」
「・・・・・・気儘之介・・・。頼むから、人目に立つような事はできるだけ・・・・・・」
と風太郎がたしなめようとした、まさにその時。
「よおおおぉっ、気儘之介じゃねぇかよっ。いつ旅から戻って来たんだよォ」
後ろから張り手のように飛んできた挨拶が・・・これまた、大きな声なのだ。
あぁ・・・・・・。
風太郎は、胸を押さえた。
「伊佐? 懐かしいぜっ。元気だったか?」
伊佐とは、梅婆さんに飯を食わせてもらっていた頃、付き合っていた飲み仲間である。 「何だよぉ、その格好はっ。 いつもの格好付け屋のおめェらしくねぇじゃねぇかよっ、こいつぅ。 おらおらっ、おーいっ、気儘の奴が帰って来やがったぜぇっ」
「何だよぉ、その格好はっ。 いつもの格好付け屋のおめェらしくねぇじゃねぇかよっ、こいつぅ。 おらおらっ、おーいっ、気儘の奴が帰って来やがったぜぇっ」
その声に何だってぇとばかりに、何人かの長屋の者が顔を出した。
江戸の長屋者は何故だかみんな、物見高い。
「チックショーっ、気儘ぁっ。おいら、お前に将棋で勝ち逃げされてたんだぜっ」
「よぉ、忠太。え、そうだったかい?じゃぁ、これから一勝負やってケリつけようや」
「おい・・・。源爺の店に、行くんだったよなぁ俺達。なっ、気儘之介」
風太郎の声に、あぁそうだったと気儘之介は思い直した。 「・・・おぉ。じゃぁ将棋は、また今度な」
「・・・おぉ。じゃぁ将棋は、また今度な」
暢気そうに、あはあはと笑う気儘之介である。
今度また来るのは、やめてくれと言いたかったが。
・・・・・・風太郎は、ぐっと堪えた。
それからの道場から源爺の店までは、本来なら歩いて小半刻(約1時間)ほどの距離なのだが。
今日は、思いの他に時間が掛かった。
源爺の店先の赤提灯が見えた時にはもう、風太郎は空腹からではなく心労から、ふらふらになっていた。
「何だよ、風太郎。俺に会えてお前は、嬉しくはないのか」 「嬉しい。嬉しいのだが」
「嬉しい。嬉しいのだが」
「うん」
「本当に、凄く嬉しいのだが・・・」
「うん」
・・・・・・一体、何と言ったものだろう。
あれこれ考えあぐねて、ようやく唇から洩れた言葉は。
「うれしいのだが、つかれる・・・」
その時。
「まぁあああーっ。気儘之介じゃないのぉ」
・・・赤提灯の影から客を、見送っていたものか・・・。
年頃の女の、頭に鳴り響くような甲高い声がする。
「あれ・・・・・・? お艶か?」
 この店の看板娘のお楽の声にしては、声が黄色い。
この店の看板娘のお楽の声にしては、声が黄色い。
「お楽は?」
二人共ここへ来るのは久し振りなので、様子がわからない。
「もぉおおーっ。お楽、お楽って。この店の看板は、お楽だけじゃないのよぉ」
「・・・だって、おめぇは。・・・なんっにも作れねぇじゃぁねぇか、酒専門で」
と、これは気儘介。
恨めしげに、お艶が髪を掻き揚げた。
「・・・うん、もぉ・・・っ、意地悪ねぇ。あたしにだって、海苔の一枚くらい炙れるわよ。さぁ、お入りなさいな。お楽、気儘之介と風太郎よ。お楽」
「気儘と、風太郎が?ホントにっ?」 
中から懐かしい声がして、お艶よりいくらか若い女が、顔を出した。
お艶と違って、いかにも働き者の出で立ちである。
二人が以前からよく知っている、前掛けに襷掛けの姿だ。
その筈なのに、・・・・・・何か。
何かが、昔の印象と違っている。
「・・・・・・お楽・・・?」
何が違うのか思いつかなくて、二人は顔を見合わせた。
 「あぁ、知らなかったのね。お楽も去年かしら。夫婦(めおと)になったのよ」
「あぁ、知らなかったのね。お楽も去年かしら。夫婦(めおと)になったのよ」
「・・・・・・っ、それでか」
思わず、二人の男の声が揃う。
・・・昔馴染みの顔が、一人前の人妻の顔になっていたのだ。
たった一、二年の間に、一体どれほどの様子が変っていくことか。
気儘之介の心には、涼風が吹く。